

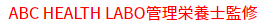
コンドロイチンっていったい何なのか、みなさんはご存知でしょうか。
「名前は聞いたことあるけどよく知らない……」という方も多いのではないでしょうか。
そこで今回は、コンドロイチンの正しい知識を管理栄養士が詳しく解説していきます。
簡単解説!コンドロイチンってよく聞くけどそもそも何?
コンドロイチンとは、ムコ多糖類の一種で、正式名称は、コンドロイチン硫酸と言います。
関節軟骨だけではなく、目の角膜、耳(内耳)、お肌、椎間板、血管、腱、細胞と細胞をつなぐ結合組織など、全身に幅広く存在(分布)しています。
コンドロイチンと聞くとなんとなく、肩や腰、膝などの関節痛にきくイメージがある方も多いと思います。
まさにその通りで、コンドロイチンは軟骨内で水分を溜め込むスポンジのような役割をしているので、不足すると軟骨は弾力性や保水性を失い、関節痛を起こす原因になります。
他にもコンドロイチンには以下のような働きがあります。
・組織に水分や弾力を与える
・全身の細胞へ酸素や栄養分の運搬を行う
・軟骨を丈夫に保ち関節痛を和らげる
・角膜の保護
からだの中で、さまざまな役割を担っていることが分かりますね。
グルコサミンとの違いは?
コンドロイチンと同じくらい有名な、グルコサミン。
グルコサミンはヒアルロン酸やコンドロイチンの原料で、関節の動きをスムーズにするのに役立つと言われています。
他にも、美しい肌を作ったり、冷え性を改善して関節痛を緩和することが分かっており、最近では美容系や関節痛に役立つ健康食品、また化粧品の成分としても注目されています。
コンドロイチンとグルコサミンの共通点は、どちらも関節痛の緩和に役立ちます。
しかし、それぞれその働き方に違いがあるのです。
コンドロイチンは、医薬品成分では「コンドロイチン硫酸」と呼ばれ、関節軟骨に弾力性や保水性を与え、「軟骨を守る」ことで、関節痛を緩和します。
一方で、グルコサミンは、関節の「軟骨を構成する成分」の原料となり、関節軟骨の健康維持に役立てられます。
コンドロイチンとグルコサミンを食べ物でとることはできる?
コンドロイチンとグルコサミンは食品中にも存在しているので、食べ物から摂取することができます。
コンドロイチンは鶏の皮や軟骨、フカヒレ、イカ、ナマコ、うなぎ、すっぽんなどの動物性食品に多く含まれ、
グルコサミンは、えびやかになどの甲殻類の殻に多く含まれています。
しかし、多く含まれている食材がわかっていても、なかなか毎食食べるのは難しい場合もありますよね。
グルコサミンは健康食品として、コンドロイチンは医薬品から健康食品まで様々な商品が販売されています。
配合されている量もそれぞれですので、薬局で尋ねてみるとよいでしょう。
グルコサミンは、かにやえびの殻を原料にしているものもあるため、甲殻類アレルギーのある人は原材料を必ず確認するようにしましょう。
そして、コンドロイチンを含む商品については、できれば正式名称の”コンドロイチン硫酸”と書かれたものを選ぶと良いかもしれませんね。
38 人が「いいね!」しました。

健康食品ではない、医薬品の力を試してみませんか。
コンドロイチンZS錠は、OTC医薬品で唯一コンドロイチン
硫酸エステルNaを1,560mg配合(1日量)した医薬品です。









